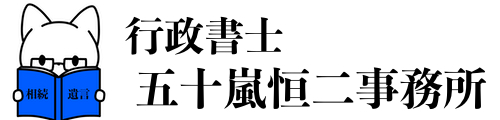遺言執行者が「必ず必要」となる相続手続きとは?
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
一般的な相続では、「遺言執行者」の選任は必ずしも必要ではありません。しかし、故人が遺言によって、「認知」、「推定相続人の廃除」、「推定相続人の廃除の取消し」をしている場合には、必ず、法定の「遺言執行者」となる人が必要となります。これらの手続きは、相続人や相続の代行を依頼されただけの人では、行うことが認められていません。
認知の方式(民法第781条第2項)
認知は、遺言によっても、することができる。
認知の届出(戸籍法第64条)
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従って、その届出をしなければならない。
遺言による推定相続人の廃除(民法第893条)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
推定相続人の廃除の取消し(民法第894条)
1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
遺言執行者は、どうやって決めればいいの?
遺言執行者は、遺言者が、遺言によって指定するか、又は、第三者に指定してもらうように委託することができます。
遺言によって指定されていないときは、家庭裁判所に申立て、遺言執行者を選任してもらいます。
遺言執行者の指定(民法第1006条)
1 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
遺言執行者の選任(民法第1010条)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
遺言執行者となるには、遺言によって指定されるか家庭裁判所にて選任される必要がありますが、未成年者と破産者以外の人であれば、相続人や相続の代行を依頼された人でも就くことができます。
遺言執行者の欠格事由(民法第1009条)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。